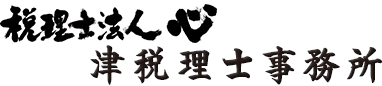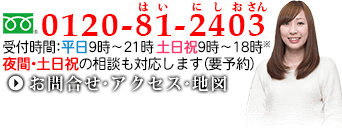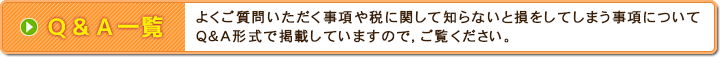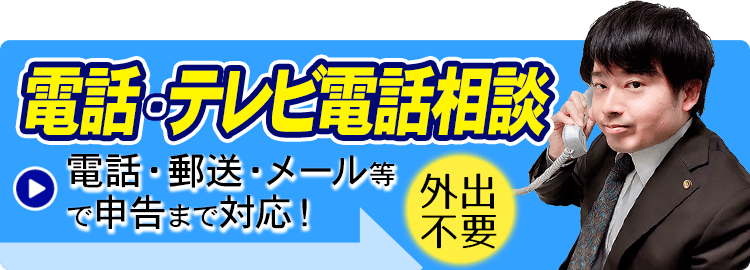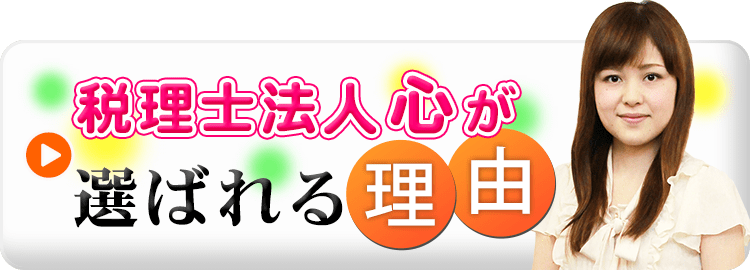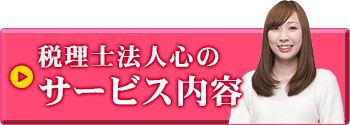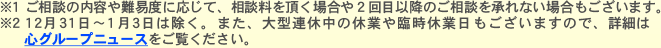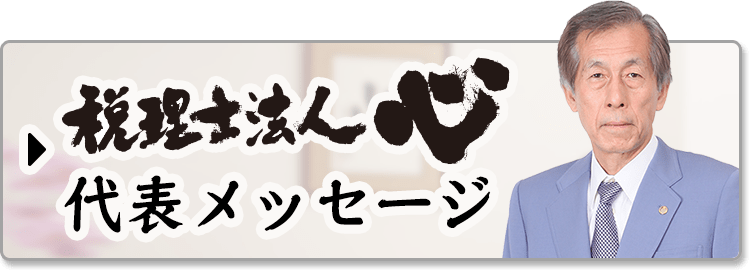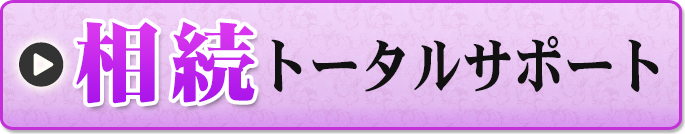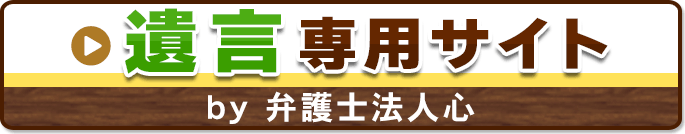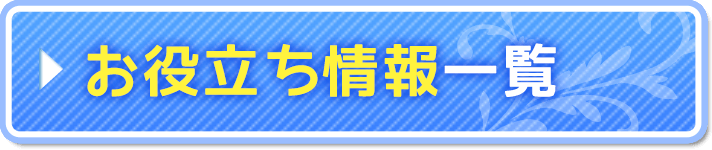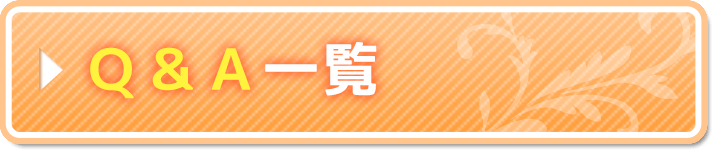生前贈与の契約書がない場合に起こり得るトラブル
1 贈与を受けた人に対し、死後に返還請求がなされるおそれがある
まず、法的なトラブルについて説明したいと思います。
具体的には、贈与を受けたはずの財産について、死後に他の相続人から返還請求がなされるというトラブルです。
贈与された財産は、贈与を受けた人に権利が移ります。
このため、贈与を受けた人は、自由に贈与された財産を利用したり処分したりすることができます。
また、贈与を受けた人は、贈与の履行を受けた以上、後日、贈与をした人やその関係者からその財産の返還を求められたとしても、その財産を返還する必要はありません。 これが、本来あるべき贈与の姿です。
ところが、贈与契約書を作成していないと、上記とは異なる事態が生じてしまうおそれがあります。
贈与を受けた人が亡くなったあとに、他の相続人が亡くなった人の預金の出入金記録を調査し、出金がなされていることを認識したとします。
他の相続人から贈与を受けた人に対し、出金についての問い合わせがあり、贈与を受けた人が、その出金は贈与されたものであると回答を行ったとします。
その回答に、他の相続人が納得した場合は問題ないのですが、納得しなかった場合は厄介な問題が生じます。
回答に納得しなかった他の相続人が、実際には贈与はなされていないはずであると主張し、亡くなった人の口座からの出金が不当に取り込まれたものであると主張し、贈与を受けた相続人に対し、返還請求を行ってくる可能性があります。
こうした返還請求がなされ、裁判所に訴訟が起こされる案件は、しばしばあります。
このような場合、贈与を受けた相続人は、口頭で贈与を受けたとの主張、立証を行い、多額の出金を返還する必要はないとの反論を行うこととなります。
しかし、贈与契約書が作成されていない状況で、贈与を受けたとの証明は、どのように行えば良いのでしょうか?
結局、贈与を受けた人が、自己申告で説明する以外に手がない状況に陥ることが多いです。
自己申告での説明が裁判所に受け入れられるかは、事案によってまちまちです。
このような自己申告での説明が裁判所に受け入れられなかった場合には、裁判所が不当に財産を取り込んだとの認定をしてしまい、出金を返還すべきとの判決を行ってしまう可能性も、十分にあるのが実情です。
このため、本当は贈与を受けたのに、贈与を受けたとの証明ができないばかりに、贈与されたはずの財産を返還しなければならない状況に追い込まれてしまうことが往々にしてあります。
それでは、上記のような事態に追い込まれることを避けるためには、どうすれば良かったのでしょうか?
解決策は、贈与を受けてことを証明する材料を残しておくことです。
贈与を受けたことの有力な証拠は、贈与契約書です。
亡くなった方の筆跡で贈与契約書が作成されており、実印等の、本人が管理しているはずの印章できちんと押印がされている場合には、二段の推定というルールが働きますので、基本的には、裁判になったとしても、亡くなった方の意思で贈与がなされたとの判断が行われることとなります。
このような強力な証拠を残しておけば、あとで贈与を受けた財産の返還を求められるような事態に追い込まれる可能性は、かなり減らすことができます。
2 名義財産や預け金として相続税が課税されるおそれがある
次に、税金のトラブルについて説明したいと思います。
贈与されてはずの財産について、本来は課税されないはずの相続税が課税されてしまうというトラブルです。
相続税が課税されるケースの場合、生前に贈与がなされているかどうかが問題となることがあります。
相続人や受遺者に対し、相続日の7年超前に贈与された財産については、相続税は課税されないこととなっています。
また、相続人や受遺者ではない人に対して贈与された財産は、贈与の時期に関係なく、相続税は課税されないこととなっています。
このように、贈与済みの財産については、相続税が課税されないこととなるケースがあり得るのです。
ところが、贈与契約書を作成していないと、上記1と同じような問題が発生してしまいます。
亡くなった人からの現預金の移転について、税務署がどのような理由で現預金が移転したかについて、説明を求めてくることがあります。
これに対し、贈与を受けたとの説明を行い、税務署が納得すれば問題はないですが、納得しなかった場合は、やはり問題が生じてきます。
税務署が贈与を受けたとの説明に納得せず、贈与の実態がなかったと判断してきた場合には、贈与を受けたはずの財産が、亡くなった人の名義財産または預け金として、相続財産に含めるべきものであるとされてしまい、相続税の課税対象になるとされてしまうおそれがあるのです。
贈与を受けたはずの財産が相続税の課税対象とされてしまうと、その分の相続税が加算されることとなり、より多くの相続税を納付しなければならなくなってしまうおそれもあるのです。
上記のような事態を避けるためには、やはり、贈与を受けたことを証明する材料を残しておくことが重要です。
相続税との関係では、第一次的には、贈与を受けた人が自由に財産を管理、処分している実態があるかどうかが重視されますが、贈与契約書が作成されているかどうかも考慮されます。
このような証拠を残しておけば、贈与の実態があったかどうかが争われる可能性を低くすることができます。